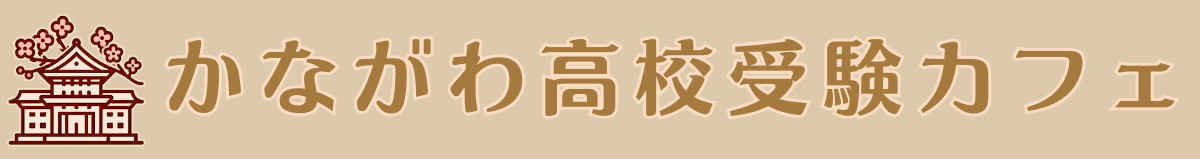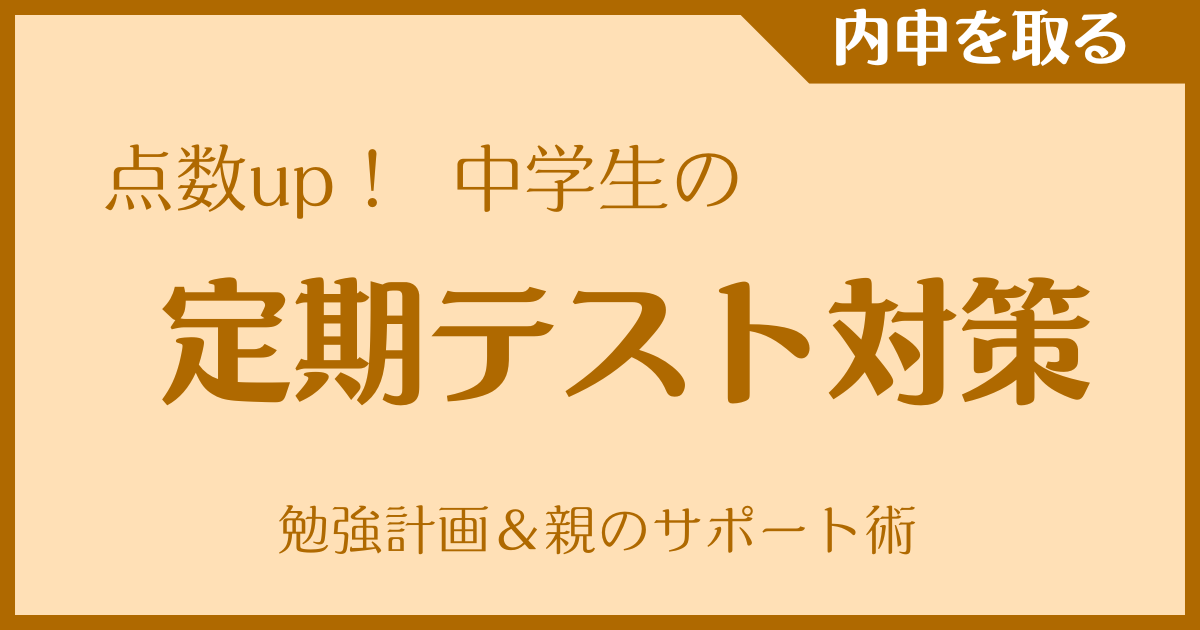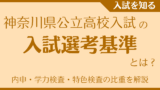定期テストは内申点に直結する重要なイベント。高校受験では内申が合否を大きく影響するため、早いうちから対策が不可欠です。本記事では
- 定期テストの基礎知識
- 教科別の勉強法
- 保護者ができるサポート
までを網羅的に解説。点数アップと内申向上につながる実践的なヒントを紹介します。効率的に成果を出したい方はぜひ参考にしてください。
中学生の定期テストとは?|内申との関係と重要性を理解しよう
定期テストは高校受験に直結する「内申点」と深く関係しており、その重要性は想像以上に高いものです。なぜ定期テストが重要視されるのか、そして中間・期末テストの違いや年間スケジュールについて詳しく解説します。
なぜ定期テストが重要なの?
定期テストは単なる学力の確認にとどまらず、高校受験にも関わる重要な評価材料です。そのため、学期ごとのテスト結果が進路選択に影響します。神奈川県の高校入試における内申点の仕組みや算出方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
中間テスト・期末テストの違いと年間スケジュール
定期試験のスケジュールは、学校の学期制度(3学期制/2学期制)によって異なります。通っている中学校がどちらの制度を採用しているかをまず確認しましょう。
■ 3学期制の中学校の場合
| 学期 | 試験名 | 実施時期(目安) |
| 1学期 | 中間 | 5月中旬~5月下旬 |
| 期末 | 6月下旬〜7月上旬 | |
| 2学期 | 中間 | 10月上旬~10月中旬 |
| 期末 | 11月下旬〜12月上旬 | |
| 3学期 | 学年末 | 2月下旬〜3月上旬 |
■ 2学期制の中学校の場合
| 学期 | 試験名 | 実施時期(目安) |
| 前期 | 中間 | 6月上旬〜中旬 |
| 期末 | 9月上旬〜中旬 | |
| 後期 | 中間 | 中3:11月上旬〜11月中旬 中1・中2:12月上旬~12月中旬 |
| 学年末 | 中3:2月上旬~2月中旬 中1・中2:2月中旬〜2月下旬) |
定期テストまでの学習スケジュール|いつから何を始める?
定期テストで高得点を取るには「テスト直前に詰め込む」のではなく、計画的な準備が欠かせません。ここでは、テスト2週間前から逆算した学習計画の立て方や、教科ごとの時間配分のコツについて解説します。
テスト2週間前から逆算した計画の立て方
多くの中学校では、テスト2週間前に試験範囲が発表されます。これを起点に、次のようなステップで計画を立てましょう。
【ステップ1】最終ゴール(テスト当日)から逆算する
テスト直前は、知識の確認や暗記科目の仕上げに充てる時間です。テスト前1〜2日は新しいことを身につけるより、今までやってきたことが定着しているかの確認にあてましょう。
【ステップ2】1週間前までに「インプット」を終える
まずは問題を解き進めるために「知識のインプット(理解・暗記)」からスタートです。学校のワークや教科書内容を活用して知識の理解・暗記、問題演習などを進めていきましょう。
多くの中学校で定期試験に合わせて学校のワークなどの提出物が要求されます。この提出物を通して基本事項をおさえていきましょう。基礎内容の習得はテスト1週間前を目安に終わらせます。次のステップの基礎となるのでしっかり定着させましょう。


試験前に力を入れたい科目に注力できるよう、やらなければいけないことは早めに解決しておきましょう。
【ステップ3】残りの1週間は「アウトプット」に集中
過去問や予想問題、学校ワークの解き直しなど、実践形式での演習を行います。間違えた問題はすぐに解説を確認し、理解を深めましょう。
~ポイント~ 演習のときには「解ける問題を飛ばす」というのも選択肢!
特に数学などの思考中心の問題は1題に時間がかかるので、「こういう方針で解く」というのがイメージできる問題を飛ばしていきましょう。その分、解き方のイメージができない問題や、過去に間違った問題の類題に力を入れると解ける問題の幅が広がると思います。


解き方がわかる問題は試験1~2日前の確認で十分だと感じています。
こうした流れを、教科ごとにスケジューリングすることで、効率的に全体をカバーできます。
効果的な勉強法|苦手克服と得点アップを両立するには
定期試験対策は限られた時間で多くの教科をバランスよく対策する必要があります。そのためには教科ごとの性質に応じた勉強のしかたや時間のかけ方が重要です。ここでは、暗記型科目と理解型科目への取り組み方の違いや、効率的な復習方法について解説します。
【基本の考え方】
- 暗記系(社会・理科の用語,英単語など)は早めに手をつけ、何度も繰り返す。
- 積み重ねが必要な教科(数学・英語の文法)は直前詰め込みが効きづらいため、早い段階から手をつけ課題をあぶり出す。
- 得意・不得意によって配分を調整。苦手科目には多めに時間を割く。
暗記系は繰り返しが重要
英単語・漢字・歴史の用語といった「暗記中心科目」では、短時間でも繰り返し取り組むことが得点力アップの鍵になります。1回の勉強で完璧を目指すのではなく、3回・5回と復習を重ねることで記憶が定着します。
思考系は解けなかった問題のあぶり出しから
数学や理科の計算問題・国語の読解など「理解重視科目」では、問題の意味や構造を理解することが先決です。わからないまま何問も解いても効果は薄いため、前提として基礎用語や公式の意味を正確に押さえることが必要です。その上で「解ける問題」「解けない問題」を演習ではっきりさせ、「解けない問題」を減らしていくのが基本的な対策方針になるかと思います。
チェック式問題演習のススメ
「解けない問題」を明確にする方法として“チェック式問題演習”を紹介します。といっても『問題演習を行う際に、間違えた問題には✓をつける』というシンプルなものです。2周目以降も間違えた場合は✓の数を増やし、逆に正解した問題は✓を消していきます。
最後の確認時に✓が多い問題に注力し、逆に少ないところはそこまで時間を割かない といった勉強時間の効率化が狙えます。
次の一歩へ|おすすめ教材と個別対策ガイド(後日公開予定)
定期テスト対策の基本が身についたら、次は「教科別」「時期別」に応じた対策へと進みましょう。ここからは、さらなる得点アップや苦手克服のための個別対策について、次の記事で詳しく解説していきます。
教科別・時期別の勉強法を徹底解説(後日公開予定)
定期テストの直前、長期休み、学年の切り替えなど、時期によって適した学習方法は変わります。また、英語や数学など教科ごとの特徴に合わせた対策も重要です。
「いつ・どの教科にどう取り組むか」の具体的な戦略を解説予定です。
本当に使える!中学生向けおすすめ問題集(後日公開予定)
市販の問題集は数多くありますが、目的や学力に合ったものを選ぶことが大切です。
定期テスト対策に本当に使える問題集を教科別に厳選して紹介します。効果的な活用法についても詳しく解説予定です。
保護者ができるサポートとは?子どもがやる気になる声かけ例
定期テストに向けて努力するのは子ども自身ですが、保護者の関わり方次第でそのモチベーションや成果は大きく変わってきます。特に中学生は思春期の入り口にあり、親の言葉や態度に敏感な時期。過干渉や否定的な言動は逆効果になりかねません。
ここでは、家庭でできる環境づくりや、前向きな声かけのコツを紹介します。子どもが自発的に勉強に取り組めるようになるために、親ができる“ちょっとした工夫”を押さえておきましょう。
こどもが「勉強に向き合える環境」の作り方
中学生が集中して勉強できるかどうかは、家庭内の学習環境が大きく影響します。学力向上をサポートするためには、次のような環境整備が有効です。
学習スペースの確保と整理
こどもが安心して集中できるスペースを作ることが第一歩です。リビングでも個室でも構いませんが、以下の点に配慮すると良いでしょう。
- 机の上はスッキリと:不要なものは置かず、教材と文房具だけを揃える。
- 照明と姿勢に配慮:目に優しいライトを使用し、椅子や机の高さも見直す。
- スマホの置き場所:勉強中は見えない場所に置く、タイマー利用で制限するなどルール化。
特にスマホについては視界に入るだけでも集中力が阻害されることが知られています(大阪大学「情報通信機器と利用者の認知に関する心理学的研究」概要)。電源を切るだけでなく勉強する空間には置かないようにした方が良いでしょう。


誘惑を振り切るためにエネルギーを使うよりも、そもそも誘惑が無い環境をつくる方が良いでしょう。
スケジュールを共有し、見守る姿勢
勉強の予定やテスト日程を家族で共有することで、子ども自身が「見られている」「応援されている」と感じやすくなります。
- リビングのカレンダーにテスト日程や目標を書き込む
- 1週間ごとの勉強計画を一緒に立てて貼り出す
大切なのは、「計画を守らせること」ではなく「自分で管理する力を育てること」です。口出ししすぎず、見守る姿勢を心がけましょう。
やる気を引き出す言葉
子どものやる気を高める声かけには、ちょっとした“コツ”があります。声掛けの基本は「承認」です。もちろん「約束を破る」など一線を越えた場合には叱ることは必要ですが、基本は日々の何気ない努力や成果を見つけ出して承認してあげることが重要です。「頑張ってるね」「前よりできるようになったね」といった具体的な努力への共感は、こどもの自信を育てます。
まとめ|定期テスト対策は「情報・計画・継続」がカギ
中学生の定期テスト対策では、まずテストの仕組みやスケジュールを正しく理解することが重要です。次に、テスト2週間前から逆算した計画的な学習を心がけ、教科ごとの特性に合わせた効果的な勉強法を取り入れましょう。さらに、間違えた問題の見直しや復習の継続が得点アップに直結します。保護者のサポートも、環境づくりと前向きな声かけで子どものやる気を支えます。これらのポイントを押さえて、情報収集・計画・継続の3つを軸に取り組むことが、定期テスト成功のカギです。