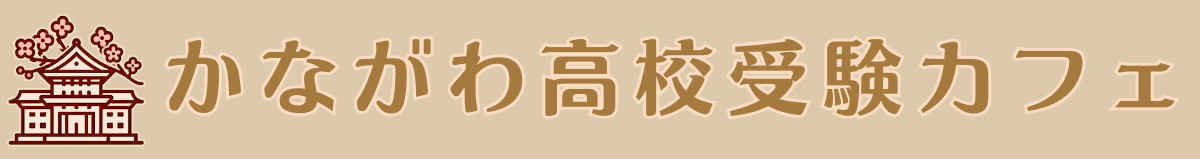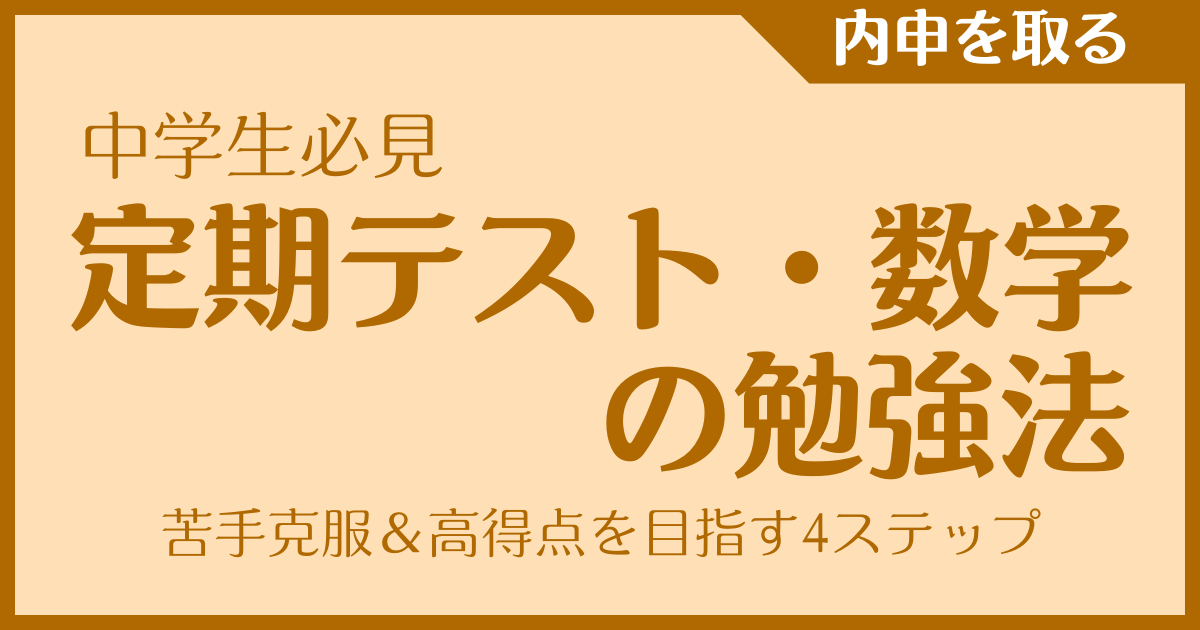中学の数学定期テストは、勉強のやり方次第で大きく点数が変わります。「ワークをやったのに点が伸びない…」という悩みも、正しい手順と教材の使い方を知れば解決できます。
この記事では、効果的な勉強法や問題集の活用方法、そして間違いを確実に減らすコツまで詳しく解説します。今日から取り入れられる勉強の仕方で、次のテストの自己ベストを目指しましょう。
なぜ苦戦する?中学生が数学でつまずく理由とは?
数学が苦手になる主な原因は4つあります。
- 計算ミスやスピード不足など基礎計算の不安定さ
- 文章題を正しく読み取れない読解力不足
- 公式を意味理解せず暗記に頼る学習
- 途中式や思考過程を省く解き方
です。これらは少しずつ積み重なり、得点力低下につながります。
基礎計算の不安定さ
数学が苦手になる大きな原因の一つが、正負の数や文字式,方程式といった基礎計算の不安定さです。途中で符号を間違えたり分数や小数の扱いに迷ったりすると、正しい解法を知っていても得点に結びつきません。特に中学では1年生内容の計算力が2・3年生の単元にも直結するため、苦手を放置すると学年が上がるほど差が広がります。計算はすべての土台となるため、早い段階で安定させることが必要です。
文章題を「日本語の問題」として読めない
文章題を苦手とする人は多いです。多くの原因は、数学以前に日本語としての理解が不十分なことです。条件や数値、問いの内容を正しく整理できないまま式を立てようとすると、解き方が見えてきません。例えば「AはBより3多い」という表現を「A=B+3」と読み替えるなど、文章を数式に変換する力が必要です。
公式の意味を理解せず暗記に頼る
数学の公式を丸暗記して使おうとすると、少し条件が変わっただけで対応できなくなります。例えば「三角形の面積=底辺×高さ÷2」も、底辺や高さの取り方をおさえていないと対応できない問題が出てきます。また意味を理解せずに覚えると、忘れた瞬間に使えなくなり解ける問題の幅も狭まります。公式は成り立ちや使い方を確認し、使い方や「どんなときに使えるのか」までセットで覚えることが重要です。
途中式や思考過程を省略する
途中式を書かずに答えだけ出そうとすると、ミスに気付けず点数を落とす原因になります。また、途中式がなければ見直しもできず、間違えた原因もわかりません。効率を重視するあまり省略してしまうクセは、結果的に遠回りです。答えだけでなく、解く手順を丁寧に残す習慣をつけることが大切です。
単元・分野別に見た数学のつまずきポイント
「令和7年度全国学力・学習状況調査」によると、
- 確率やデータの活用
- 数学の用語の意味
- 図形の証明
について課題があるという分析が出ています。
必ず起こる事柄の確率について理解できているが、不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することについては課題がある。
数学の用語の意味の理解に課題がある。
統合的・発展的に考え、条件を変えた場合について、証明を評価・改善することに課題がある。また、証明したことを基に、新たに見いだした事柄を証明することにも課題がある。
国立教育政策研究所「令和7年度全国学力・学習状況調査」
数学が苦手でも伸びる!数学の克服法まとめ
基礎計算を安定させる勉強法
基礎計算の安定は数学全体の成績アップに直結します。まずは毎日10分程度、計算単元の練習を続けましょう。計算ミスを減らすコツは「ゆっくり正確に解く」ことです。まずは基本的なルールや計算方法を復習し、問題集の計算問題を繰り返すのがおすすめです。また間違えた問題をピックアップして解き直しすることで、正しい計算方法が身についているかが確認できます。
文章題の読解ポイント
文章題を解くには、問題文を「日本語の文章」として丁寧に読む力が必要です。条件や数値を線で囲んだり、重要な言葉にマークをつけたりして整理しましょう。また、問題文の意味を自分の言葉で簡単にまとめてみると理解が深まります。たとえば「AはBの3倍」のように「~~は〇〇の△△」といった形で条件を読み替えることができれば、関係を式に置き換えやすいです。読解力が上がると、問題の全体像が見えやすくなり、解く手順もスムーズになります。
公式の理解と使いこなし
公式はただ覚えるだけでなく、その意味や成り立ちを理解することが大切です。公式は文字を使って表現されるものが多いですが、それらの文字が何を指しているのかをしっかりおさえましょう。その上で実際の問題で使いながら慣れていくことが重要です。
また、公式に対して証明ができるのが理想です。公式の理解が深まるだけでなく、証明過程が問題を解く過程に応用できることも多いです。繰り返し練習し、公式を自分の武器にしましょう。
途中式の徹底
途中式を書くことは、問題を正確に解くために欠かせません。計算ミスや符号処理のミスを防ぎ、自分の考えを整理する助けになります。また、途中式があれば見直しがしやすく、定期試験の問題のよっては部分点をもらえる可能性も高まります。焦って答えだけを書かず、どんなに簡単な問題でも途中式を丁寧に残す習慣をつけましょう。そうすることでミスを減らし、理解を深めることができます。
定期テスト前の数学勉強法:4ステップで点数アップ
「何から手をつければいいか分からない」「問題集をやったけど点数につながらない」…そう感じている中学生や保護者は少なくありません。定期テストの数学対策ではやみくもに勉強するのではなく、段階を踏んで進めることが極めて重要です。
ここでは、理解 → 練習 → 実戦 → 振り返りという4ステップで、効率的かつ効果的な勉強法を紹介します。
ステップ① 教科書とノートで理解を深める
最初にやるべきことは「解き方の意味」を理解すること。そのためには、教科書の例題や授業ノートを見返すのが最も効果的です。特に以下のポイントをチェックしましょう:
「分かったつもり」で次のステップに進むと、応用問題で必ずつまずきます。理解があいまいな問題は、解説を読み進めて1つずつ解き方を理解していきましょう。
ステップ② ワークや塾教材で「練習」する
理解しただけでは点数は伸びません。次に必要なのは「手を動かして、解けるようになる」こと。ここで使うのが、学校ワークや塾のテキストです。
練習のポイント
- 同じタイプの問題を繰り返し解く
- わからなかった問題には印をつけておく
- 解説を読んで納得できたら、自力で再トライ
この段階では、「間違えること」はむしろ歓迎すべきチャンスです。大切なのは、その間違いをどう扱うか。次に活かすための「印」として記録しておきましょう。
ステップ③ 過去問・予想問題で「実戦形式」に慣れる
ある程度ワークで解けるようになってきたら、過去問や予想問題に挑戦します。目的は以下の通りです。
- 「時間内に解く」練習(時間配分の感覚をつかむ)
- 「初見問題」に対する対応力を養う
- 出題傾向や形式に慣れる
このとき、「何点取れたか」だけでなく、
- どの問題で間違えたか?
- 間違えた原因は?(計算ミスか?理解不足?)
- 同じタイプの問題を次に解けるか?
といった分析視点を持つことが重要です。
ステップ④ 間違い直し・振り返りで定着させる
多くの中学生が見落としがちなのが、この振り返りのステップです。「できなかった問題を解き直す」ことで、はじめて知識が定着します。同じところで間違えた場合は、もしかしたら理解が不十分かもしれません。2日後や前日に再トライして、解けるようになったかを再度確認しましょう。
やりっぱなし卒業!過去問・問題集の活用術
「問題集を何冊もやったのに点数が上がらない」…という声も。実はやる問題の“量”よりも、“やり方”が重要なのです。ここでは、過去問や問題集を「やりっぱなし」にせず、確実に実力に変える方法を紹介します。
過去問は「試験1週間前から」でOK?タイミングと注意点
過去問は、本番を想定した「実戦練習」の道具。そのため、テストの1週間前〜3日前あたりに取り組むのが理想的です。ただし、以下の点に注意しましょう。
- まだ習得できていない範囲があるうちは、過去問に手を出さない
- 「満点を取る」ことより、「自分の弱点を洗い出す」ことを目的とする
- 時間を測って取り組み、緊張感を持って解く
過去問でつまずいた問題は、類題を教科書やワークから探して復習し直すのが鉄則です。過去問を“解いて終わり”にしないよう、解き方を理解する→解き直すのサイクルが重要です。
問題集は2周以上が基本。弱点は徹底的に!
問題集は「1回解いたら終わり」ではなく、最低でも2周する前提で取り組みましょう。1周目は試験範囲の出題内容把握と「解ける問題」と「解けない問題」の選別です。問題集を何度も解く といってもすべての問題を解くのは非効率的です。2周目以降は解けない問題にフォーカスを当てて、少しでも弱点を減らしていくことが狙いになります。

幅広く問題集に手をつけるのはしっかり理解ができてから。不十分な内容がある時点では、1つの問題集をやりこむ方が良いと思います。
テスト勉強の落とし穴と、点数を上げる3つのコツ
「時間はかけたのに思うように点が取れなかった…」という経験は、多くの中学生に共通する悩みです。ここでは、数学のテスト勉強でよくある“落とし穴”と、その改善ポイントを解説します。
「時間はかけたけど意味がなかった」勉強の特徴
いくら長時間勉強しても、やり方を間違えていると成果にはつながりません。よくある“ムダ勉強”のパターンは
- 解ける問題ばかり何度も解く(=負荷がかからない)
- 答えをすぐ見て納得して終わりにする(=記憶に残らない)
- 間違えた問題をそのままにする(=同じミスを繰り返す)
これでは「やったつもり」になっているだけです。
改善ポイント
- 「解けない問題」を見える化する。
- 解き直しをするサイクルをつくる(例:2日後に同じ問題を解き直す など)
「ケアレスミス」が減らない理由と改善策
計算ミスや符号ミスなどの「ケアレスミス」は、実はうっかりではなく準備不足から生まれることが多いです。
よくある原因
- 手を動かす練習量が足りない(=作業スピードが遅くなる)
- 問題文の読み飛ばし
- 途中式の書き方が雑(=確認しづらい)
改善策
- 条件や問われている内容に線を引く
- 計算や式変形の途中式を省略しない
まとめ|定期テストの勉強法を変えれば、数学は必ず伸びる
数学の定期テストは、「理解→練習→実戦→振り返り」の4ステップと、過去問や問題集の正しい使い方で確実に伸ばせます。重要なのは量より質、そして「できなかった問題をできるようにする」こと。計算力、文章題読解、公式の理解、途中式の徹底という基礎を固め、ケアレスミスを減らす工夫を重ねれば、点数は必ず上がります。まずは試験までの計画を立て、弱点を1つずつつぶす勉強法を今日から始めましょう。