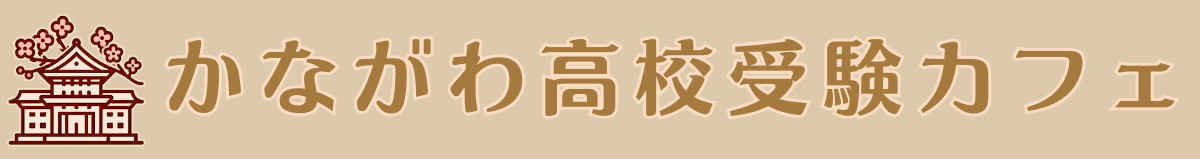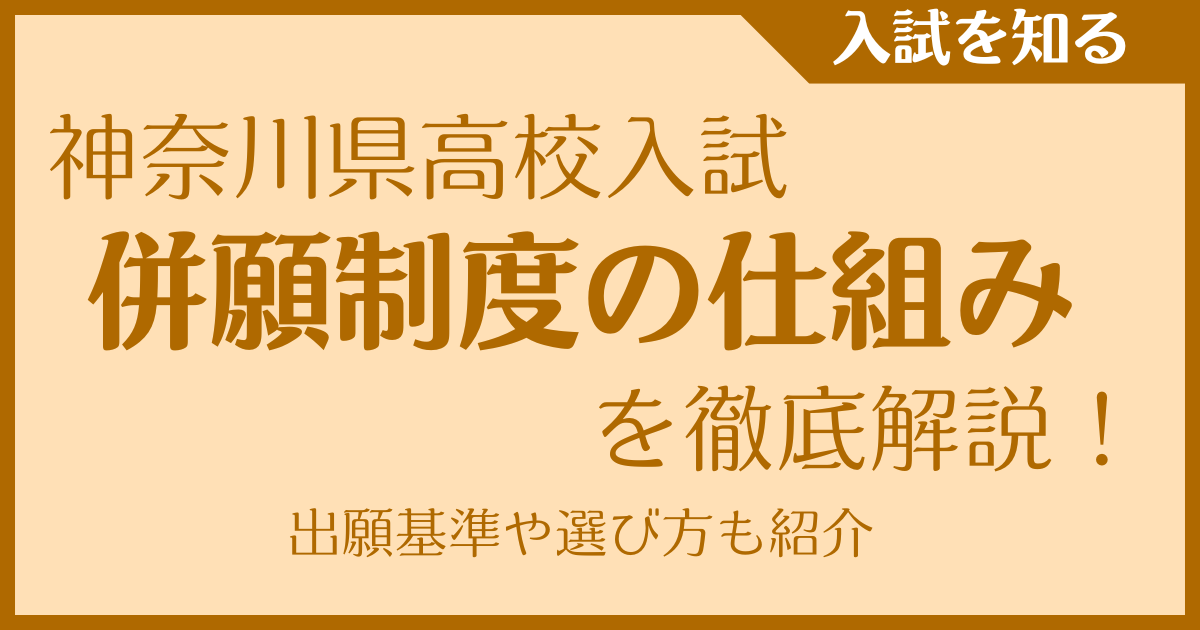「併願校ってどう選べばいいの?」「併願確約って何?」「出願基準に届かない場合はどうすればいいの?」
神奈川県の高校受験を考える上で、私立高校との「併願制度」は非常に重要な選択肢となります。
この記事では、
- 神奈川県の併願制度の概要
- 出願基準の考え方・併願校の選び方
- 基準に届かなかったときの対応策
を詳しく解説します。第一志望校を安心して受験する体制を整えるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
併願とは?
神奈川県の併願制度とは、私立高校を公立高校の「すべり止め」として受験し合格の可能性を事前に確保しておける制度です。 多くの場合、内申点や提出書類による選考基準が設定されています。出願をして合格が得られたとしても、入学辞退が可能です。
併願確約とは?
神奈川県では「併願確約」という制度が一般的です。これは、一定の内申基準を満たせば事前相談(個別相談)を通じて事実上の合格を確約してもらえる制度です。

「確約」というのは俗称で高校側はこの表現を公式には使用しません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
確約を得るには、個別相談への参加・中学校との連携が必須
高校ごとに出願基準が設けられているため、基準を満たしているかの事前確認が必要です。個別相談会などの機会で「基準を満たしていること」を確認しておく必要があります。また、調査書(内申)を活用する入試制度のため、中学校側に併願校の受験意思を伝えておく必要があります。

内申の基準を「出願の目安」として設定している高校もあります。個別相談でしっかり確認をしておきたいところです。
私立併願ができないケースもある
一部の併願制度では「公立のみ併願可」としているケースもあります。公立高校を第1志望としている場合は問題ありませんが、私立高校にチャレンジを検討している場合は併願の制約に注意が必要です。
必ずしも合格が保証されるわけではない
実際の合否は高校側の判断によります。よほどのことがなければ不合格になるわけではありませんが、受験日当日の素行などで不合格になる可能性があるようです。

塾講師の間でも、“まれに不合格になる例がある”といった話が出ることもありました。
併願入試の種類
併願の種類には「書類選考」と「筆記試験」の2種類があります。
書類選考とは?
高校に調査書などの必要書類を提出し、提出書類だけで選考する入試方法です。試験を受けるために高校へ向かう必要が無いのが大きな特徴です。
筆記試験がある併願入試
調査書などの必要書類を提出したうえで、設定された試験日に筆記試験を受験する入試方法です。一部の高校を除き筆記試験の点数によって不合格になることはありません。
出願基準について
私立高校ごとに、内申点の合計や特定教科の評定に応じた出願基準が設定されています。参照する内申については中3時点のものを見るケースが多いです。加えて、出欠状況や部活動・委員会活動といった内容も調査書を通して見られます。
出願基準については把握できている範囲で「STEP3 高校を知る」の各校紹介ページに掲載しています。詳しくはそちらをご覧ください。
出願基準に届かないときの対策法
募集要項などで提示されている基準に届かない場合でも、併願校の選択肢から外すのはまだ早いです。
加点要件の利用
内申点に届かない場合でも「加点要件」を設けているケースは多いです。検定(英検・漢検など)や部活動実績・生徒会活動など一定の条件を満たせば内申点に加点され、出願基準に届く場合があります。
個別相談の活用
直接高校へ相談し加点要素や柔軟な対応が可能か確認することで、道が開ける場合もあります。大幅に出願基準を下回る場合は難しいですが、「出願基準-1~2」程度の内申であれば個別相談の機会を活用する価値は十分にあります。
併願校の選び方
現状に近い内申水準の高校を選ぶ
確約を得るには、内申点が基準を満たしている必要があります。現在の内申から無理なく届く範囲の高校を中心に検討しましょう。
納得できる高校を選ぶ
たとえ公立高校が第一志望でも、併願校に進学する可能性もゼロではありません。万一の場合でも後悔しない、納得感のある学校を選ぶことが大切です。
受験スケジュールに注意する
筆記試験がある私立入試の受験日は公立入試の3~4日前に集中します。書類選考のみの入試であれば身体的負担は少ないですが、筆記試験を実施する併願の場合は高校へ受験しに行く必要があります。確約性が高いとはいえ、高校へ足を運び試験を受けるというのは心身ともに負担が大きいです。第1志望校受験前日に試験日程を入れないなどの受験スケジュールの配慮が必要です。
まとめ|併願制度をうまく活用しよう
公立入試や私立のオープン入試は事前に100%合格が確定する入試ではありません。自分が本当に行きたい高校に最高のコンディションで受験をするためにも、併願校という安心材料を確保しておくことはとても重要です。
一方、併願校とはいえ「もしかしたら通うかもしれない高校」でもあります。第1志望に全力を注いだ上で手が届かなかった場合、「この高校なら納得できる」高校を併願校として考えておきましょう。そのためにも
を考えておきましょう。特に併願校のリストアップと内申点の確保は重要です。第1志望や併願校の選択肢を広げるために日頃からコツコツできることを進めていきましょう。
内申についての概要や内申の上げ方のポイントは「STEP4 内申を取る」のページでまとめてあります。こちらもぜひ。