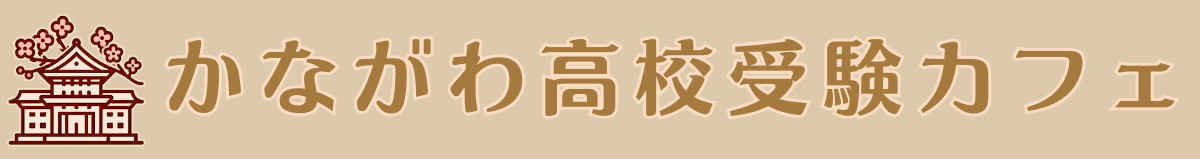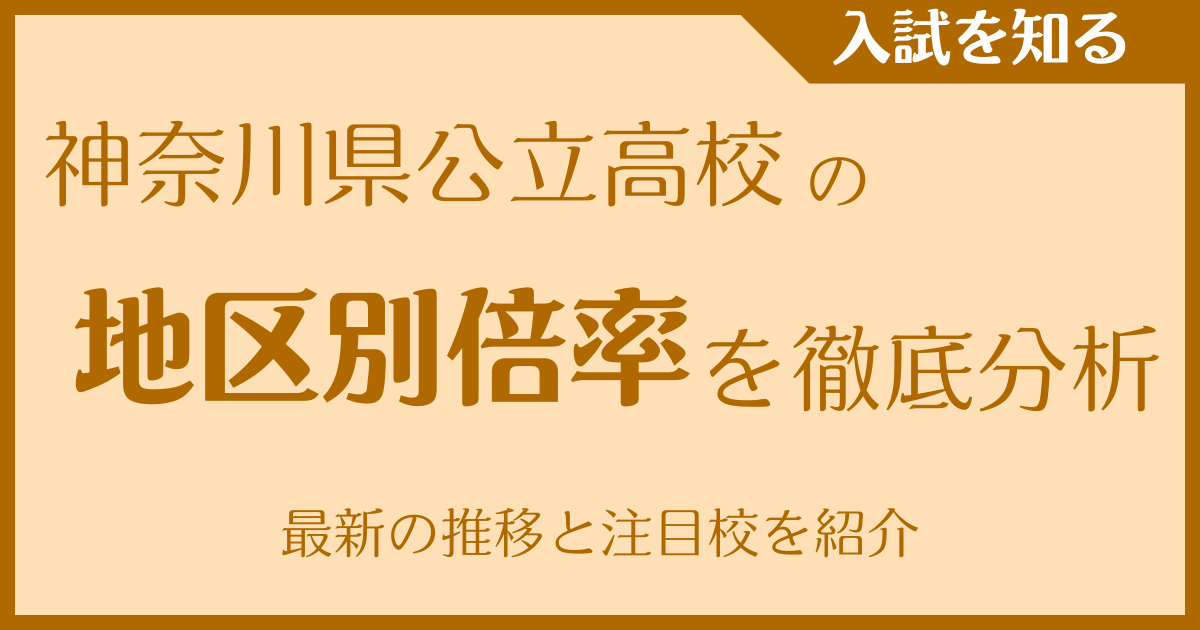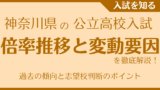倍率に関する記事の第2弾。この記事では、地区ごとの倍率に注目していきます。
そもそも倍率って?という方はこちらの記事から
倍率を見るうえでの注意点
「低倍率=レベルが低い」ではない
倍率が低くなる要因は「合格のボーダーラインが低いから」だけではありません。人口や一時的な高校の人気など、倍率を動かす要因は多くあります。倍率は受験難易度を測る指標にはなりません。
倍率は何に活用するか
では倍率は何に使えるか というと
- 「次の入試のボーダーラインがどうなりそうか」の予測
- 倍率が出たときに「志願変更をするかどうか」の指標
の2点であると思います。そのためにも「倍率の相場」を知っておくのが良いでしょう。
他にも「穴場の受験校探し」にも活用できますが、穴場=自分の行きたい高校とは限りません。志望校を決めるうえで重視すべきは倍率ではなく、自分が通いたいかどうかです。
地区ごとの倍率傾向
倍率は人口や定員数,高校の人気などが影響します。地区ごとに傾向はあるのでしょうか。比較的高校数が多い地区の傾向と、倍率が気になる高校をピックアップしました。
※地区については神奈川県HP「はいすくーる・わんだーらんど」に準拠して分類しています。
※地区ごとの平均倍率については高校別の単純平均をとっています。
横浜北地区(20校)
過去3年の地区平均倍率は1.3倍台で、少し高い水準が続いています。
要因の1つとして都市部であることによる人口の多さがあります。そのためか、過去3年で定員割れとなった高校はほぼありません。
また、「横浜翠嵐」「神奈川総合」「横浜サイエンスフロンティア」などといった上位校が多いことも、人気の高さの要因として挙げられます。
倍率が気になる高校
横浜翠嵐高校
湘南高校と並ぶ神奈川県屈指の難関校です。令和7年,6年と2年連続で倍率トップです(令和5年は神奈川総合高校(個性化)に次いでNo.2)。倍率は2.00倍近い水準が続いています。
川和高校
特色検査を実施する高校としては低めの倍率水準です。令和6年にクラスが1つ減少し少しずつ倍率は上がってきていますが、それでも1.4倍を割っています。
岸根高校
地域中堅レベル校ですが、準トップレベルの高校を抑えて比較的高倍率です。ここ3年は1.3倍前半~1.4倍前半の倍率です。特にクラス数の増減はありませんでしたので要因は不明です。
城郷高校
こちらも地域中堅レベルですが、令和6年・5年と1.4倍台の高倍率となりました。令和7年入試では1.26倍まで落ち着きました。
横浜中地区(16校)
過去3年の地区平均倍率は1.2倍台で全県平均並みです。個別に学校を見ていくと、特色検査を実施している高校(「希望ヶ丘」「横浜平沼」「光陵」)と地域準トップレベル校(「上矢部(普通科)」「市立桜丘」)を除いて1.2倍を割っています。地域中堅校は1.0倍台が多いです。
また、特色検査を実施する3校も希望ヶ丘を除いては比較的低めの倍率になっています。
倍率が気になる高校
光陵高校
特色検査を実施する1校。令和5年の入試は1.44倍と上位校としての水準でした。しかし令和6年以降は1.2倍台後半の水準が続いています。
市立戸塚高校
地域準トップレベルの高校です。令和6年までは1.2倍台と全県平均レベルでしたが、令和7年に1.06倍と大きく下がりました。クラス数の変動等が無ければ、元の水準に戻る可能性があります。
横浜南地区(17校)
過去3年の地区平均倍率は1.2倍後半~1.3倍の水準で、全県平均より少し高いです。
地域トップ校はもちろん、準トップレベル校,中堅レベル校まで1.2倍を超えている高校が多いです。トップ校の「柏陽」「横浜緑ヶ丘」は神奈川県の公立入試倍率Top10に入ることもあります。
倍率が気になる高校
横浜南陵高校
令和6年入試に1.58倍となり、県内6番目の高倍率になりました。急激な上昇により1.31倍とだいぶ倍率は落ち着きましたが、出願の目安を考えると高倍率であることに変わりありません。
市立みなと総合高校
こちらも令和6年に倍率が大きく上昇した高校です。令和7年には1.20倍と落ち着きを取り戻しました。
川崎地区(19校)
過去3年の地区平均倍率は1.17倍とやや低めですが、地域トップ校と地域中堅以下との格差が大きいです。
特色検査を実施する高校は「多摩」のみですが、準トップレベルの「新城」なども倍率の水準が高いです。
倍率が気になる高校
新城高校
個人的には令和7年入試の倍率で一番驚いた高校です。令和5年の時点で倍率は1.54倍と特色検査の実施が無い高校にしては高倍率でした。しかし、令和7年になってその倍率はさらに上がり、1.79倍となり県内2番目の倍率になりました。この地域では特色検査実施校が「多摩」のみなので、その受け皿となっている点が要因と考えられます。
市立橘高校(普通科)
数年前までは地域中堅校の位置づけですが、高めの倍率が続き合格ボーダーラインが上昇している高校です。それでもなお令和7年入試は1.53倍と神奈川県内トップクラスの倍率でした。倍率の上下動が大きい点も気になります。
住吉高校
こちらも地域中堅校の位置づけでした。令和5年の1.51倍(県内No.9),令和7年の1.53倍と高倍率になることが多く、倍率を背景にボーダーラインが上昇している印象です。
鎌倉湘南地区(14校)
地区の倍率平均は1.22倍です。ここ2年のクラス増減が目立つ地区の1つです。極端に倍率が高い高校少ないです。一方で定員割れをしている高校は1.00倍を大きく下回ることが続いています。これらの学校はクラスの削減が行われるのでは…?と思います。
倍率が気になる高校
湘南高校
神奈川県の公立2トップの一角です。倍率は1.60倍付近が続いています。
藤沢西高校
令和7年入試で倍率が1.42倍まで上昇した高校です。同年にクラスの1減を行っているため、その影響と考えられます。
鎌倉高校
特色検査を実施する高校の1つです。倍率は1.2倍台後半から1.4倍くらいで、他の実施校と比べると低めの水準です。
茅ヶ崎北稜高校
こちらも特色検査を実施する高校の1つ。ここ3年は倍率は低下傾向であり、令和7年入試では1.21倍と全県平均並みまで下がってきています。
横須賀三浦地区(10校)
地区の倍率平均は1.09倍ですが、高校数がそこまで多くは無いので平均倍率はそこまで参考になりません。倍率が1.0倍台の学校が半数近くを占めています。
倍率が気になる高校
横須賀高校
特色検査を実施する高校の1つです。倍率は1.4倍を超えることが少なく、地域トップ校としては低めの倍率が続いています。場所柄としても他地区からの流入がしにくいことから、今後もこの水準が続くと思います。
追浜高校
令和7年入試では、地域トップ校の横須賀をおさえて倍率が1.41倍まで急上昇しました。前年の「県立横須賀」の倍率が上振れているため、ボーダーライン上昇を嫌った層の志望校引き下げが考えられます。また、令和6年に1クラス減を行っています。
平塚地区(7校)
地区の倍率平均は1.03倍ですが、高校数が少なく倍率は高校ごとにばらけています。地区内では地域トップの「平塚江南」,準トップの「大磯」が志願者を集めており、他の高校は1.0倍台以下となっています。
倍率が気になる高校
平塚江南高校
特色検査を実施している高校ですが、令和5年入試では1.18倍とかなり低い水準でした。直近は1.37倍まで上昇していますが、それでも特色検査実施校としては比較的低倍率です。
平塚湘風高校
単位制普通科の高校で、倍率は下落傾向でした。令和6年は定員割れが発生。そこに令和7年の1クラス増もあり、令和7年入試では0.80倍まで倍率が下がりました。
秦野伊勢原地区(5校)
こちらも学校数は少なめです。地区の倍率平均は1.08倍です。特色検査実施校が無いこともあり、全体としては低めの倍率です。「伊勢原」を除いて倍率は低下傾向しており、他地区への流出も考えられます。
県西地区(8校)
地区の倍率平均は0.88倍です。この地区は比較的人口が少ないためか、全体として倍率が低いです。またアクセスが難しい点も、志願者が少なくなる要因であるように感じます。
倍率が気になる高校
小田原高校
特色検査を実施する高校の1つですが、倍率は1.3倍を超えることが少ないです。県西地区全般に言える志願者の少なさが要因だと思います。
県央西地区(9校)
地区の倍率平均は1.03倍です。こちらも同様にアクセスのしにくさが低倍率の要因であるように感じます。
倍率が気になる高校
厚木高校
特色検査を実施する高校の1つです。倍率には波がありますが、令和7年入試では1.14倍とかなりの低倍率となりました。
海老名高校
地域2番手校レベルの高校ですが、倍率は「厚木」を上回ることもあります。ボーダーラインの上下に応じて、「厚木」志願者が「海老名」へ流れ込むことでこのようなことが起こっていると感じます。
県央東地区(7校)
地区の倍率平均は1.14倍です。地域準トップレベルである「座間」と中堅校に位置する「大和西」との難易度のさが大きいです。そのためか、地区内の倍率は「大和」「座間」の上位2校に偏っている印象です。
倍率が気になる高校
大和高校
特色検査を実施する高校の1つ。県全体でみても倍率トップ10の常連校です。1.5倍台の倍率が一般的で、令和6年に1.42倍となりましたが、すぐに1.5倍台に戻っています。
座間高校
他地区と比べて比較的難易度が高い地域準トップレベル校です。令和5年入試では1.09倍と低倍率でしたが、令和6年の1クラス減を受けて少しずつ倍率が上昇し、令和7年入試は1.31倍となりました。
相模原地区(12校)
地区の倍率平均は1.07倍です。変動はあるものの常に1.2倍を超えている高校が少なく、クラスの増設はここ3年行われていません。
倍率が気になる高校
相模原高校
特色検査を実施する高校ですが、ここ3年は1.2倍台の水準が続いています。この傾向が特色検査実施校の中でも比較的ボーダーラインが低くなっている要因の1つであるように感じます。
相模原弥栄高校
地域準トップレベル校の位置づけですが、令和7年入試では1.38倍と地区内トップの倍率になりました。とはいえ倍率変動の大きい学校であるため、この水準が続くかは不明です。
まとめ|倍率は相場
公立高校の倍率について2記事にわたって書いてみました。
「倍率を見るうえでの注意点」でも書きましたが、倍率はあくまで「相場」であるように思います。野菜の相場が一時的に変動するように、高校の人気も変動します。
しかし、倍率が変わっても「高校自体の価値」が変わるわけではありません。高校を選ぶ上で「通いたい!」という思いが最重要であることを念頭に置きつつ、志望校の最終調整に倍率という相場を活かしていただければと思います。